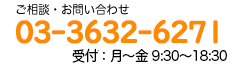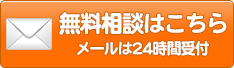http://ossforum.jp/en/node/806
1) GPL違反
* コピーレフトの概念と商用ソフトウェアの矛盾
ソースコードを公開、改変と再配布を許すことによりソフトウェアの発展を目指すコピーレフトの概念と、ソースコードは企業秘密であり秘匿して守るべき知的財産と考える商用ソフトウェアでは、そもそも考え方の根本が異なる。一方で、インターネット等で数多く公開され簡単に再利用が可能なOSSを活用して効率的に商用ソフトウェアを作成したいという欲求もあり、ここに矛盾点が存在する。
* なぜGPL違反が起こるのか
GPLに関する理解の不足が、多くのGPL違反を引き起こす。組み込み機器の場合、ハードウェアに組み込んでしまえば分からないだろうという油断もGPL違反の一因と考えられる。
* ライセンス違反に関する対処
ライセンスを契約と考えた場合は、GPL違反に対しては契約違反として係争することとなる。
2) CeBIT2005における事件
* 事件のあらまし
2005年3月にドイツのハノーヴァーで開催されていたCeBIT 2005において、GPLでライセンスされたソフトウェアを正しく利用していない疑いのある企業に対してそれを警告する公開書簡が手渡されるという事件が起きた。公開書簡を手渡したのは、gpl-violations.orgプロジェクトの創立者であるHarald Welte氏。
* gpl-violation.orgプロジェクト
このプロジェクトは、GPLでライセンスされたソフトウェアを利用している企業に対してGPLを正しく理解させ、適切に利用させることを目的として活動するプロジェクトである。
* 書簡を受け取った企業
gpl-violation.orgによると、書簡を渡した企業は13社で、Motorola、Acer、AOpenといった大企業だけでなくMicronet、Buffalo、Trendwareといった企業も対象となったという。
3) GPL違反への対応
* GPL違反の発覚とその影響
– ソフトウェアの動作や機能から疑問を持った技術者の解析によってGPL違反が発覚する場合がある。
– GPL違反が発覚すると、その企業に対するネガティブキャンペーンがネットワークを介して消費者間で広がるというリスクがある。
* エプソンコーワ(現アヴァシス)の対応例
– GPLで公開されていたOSSのコードをLinux向けの商用プリンタドライバに流用してバイナリを無償配布した。ところがそのバイナリが解析され、GPLで配布されていたコードが流用されているにも関わらず、GPLに準じた扱いとなっていなかった点が問題視された。
– コミュニティから指摘を受けた同社は、すぐに自社のウェブサイトで謝罪した。さらに当該ソフトウェアを差し替え、ライセンスを修正して公開した。コミュニティからは、この対応が好ましいものであったとの評価を受けた。
2016年8月23日