知的財産権
最近になってオープンソースソフトウエア(以下、OSS)を使いたいがどういう点に注意したら良いかという相談を受けることが多くなった。
私が最初に製品にオープンソースを組み込んだのが2000年代初頭でまだ社内標準もできてなかった頃だ。 最初は何を調査すべきかもわからず、相当時間がかけて調査をし何度も報告をしてようやく使用することがでるようになったのを覚えている。
その後その調査報告書をたたき台として社内標準が作成され、それがシステム化されたので昔よりはずいぶん楽になっている。
これまでの歴史を見るとオープンソースの前にパソコン通信の波に乗りフリーソフト(もちろん今でもある)やパブリックドメインと呼ばれたソフトウエア、さらにプログラムが著作権と認められなかった所謂「牧歌的時代」があったが、米国では1980年、日本では1985年にプログラム(ソースコード)も著作権で保護されることになった。
ここが一つの節目になるが、もう一つの大きな流れが1984年にリチャードストールマンにより創設されたGNUから始まった。
その最初の目的は完全にフリーソフトウェアで構成されるオペレーティングシステムを実現すること、それにより牧歌的時代のコンピュータユーザーのように、ユーザーを自由にしたいと考えていた。
その自由とは、以下の4つであり、後にGNU宣言として1985年3月に公表された。
- 使っているソフトウェアのソースコードを使って研究できる自由
- ソフトウェアを他の人々と共有できる自由
- ソフトウェアを修正できる自由
- 修正版を配布できる自由
この自由を守るために編み出されたのがのちに詳説する「コピーレフト」であり、この哲学のもとにLinuxをはじめ多くの優秀で効果的なソフトウエアが普及するようになった。
OSSを複雑にしている理由
オープンソースライセンスは一般的なソフトウエアライセンスの一形態であり、その根拠法は著作権法である。 その著作権法は国による差異があるうえ、日本国の著作権は付則抄(約24000文字)の除いた本文だけで全124条、条文の文字数は約72,800字でなんと日本国憲法の7倍以上の分量だ。しかも追記が続いたせいか大変読みづらく、さらにプログラムに著作権が認められたのが1985年(昭和60年)の改正時だ。
これらの関係は以下の図のようになっているため、まずは著作権からおさらいしておこう。
各省庁の説明
文化庁
文化庁では、「知的財産権」とは,知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」権利であり,以下のようなものが含まれるとしており、意外とあっさりしている反面わかりやすい。
特許庁(経産省)
特許庁では、「知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます」としてビジネスを意識した説明になっている。
さらに特許権、商標権のように書面による申請をすることにより排他的に支配できる「絶対的独占権」と、創作した時点で権利が得られる著作権のように他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」とを区別しておりやや法律を意識した説明になっている。
実は縦割りの行政庁(管轄)
両省庁ともわかりやすい説明をしてくれているが、これらの主幹行政庁(管轄)は以下のようにわかれているのだ。
①特許権、実用新案権、意匠権、商標権:特許庁
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
②著作権:文化庁
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html
③半導体回路配置利用権:一般 財団法人ソフトウェア情報センター(以下、SOFTIC)
http://www.softic.or.jp/
④育成者権(種苗法):農水省
http://www.hinsyu.maff.go.jp/
⑤不正競争防止法関連:経産省
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/index.html
⑥商号登記:法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/
主旨からいってわからんこともないが、それにしてもあまりに縦割りの組織になっている。
統括組織は「知的財産戦略本部」
これらの縦割り組織を束ねるのが2003年に成立した「知的財産基本法」に基づき、政府全体の知的財産戦略計画を毎年作成し、知的財産に関するずうよう施設の総合調整役となっている内閣総理大臣を本部長とする「知的財産推進本部」が内閣府内に設置されている、というわけだ。(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/)
この本部から今年も「知的財産推進計画2016」が五月に提出されたが、いまだにフェアユース(*1)の導入すら実現できていない著作権の後進国である日本において例年になく将来の産業発展のために前向きな提案となっている点は好感できる。
本計画書は以下のサイトからダウンロードできるが主なトピックを簡単に説明しておく。
なお、途中掲載している図は知的財産戦略本部にあるドキュメントから引用している。
[wpdm_package id=’2123′]
「知的財産推進計画2016」
1、潮流
・第四次産業革命の進展と超スマート社会(Society 5.0)への展望
・経済のグローバル化の進展
2、コンセプト
・「知的財産」の射程拡大
・「つながり」「かけあわせ」による「オープンイノベーション」 + 「オープン&クローズ戦略」を軸にした「知財マネジメント」の精緻化
・イノベーション創出への「挑戦者」の応援を基本とした制度づくり・人づくり
3、主なトピック
(1)デジタルネットワーク時代の著作権システムの構築
・著作物を利用する際には事前許諾を得ることが原則であるが、大量の情報を集積、利活用する場合などに個別の事前許諾だけでは対応できないと考えられる。
・著作物を含む情報の量的拡大と情報の利活用方法の多様化という変化に対応し、新たなイノベーションの促進に向けて、知財の保護と利用のバランスに留意しつつ、城南な解決が図られるグラデーションのある取り組みが必要。
(2)人工知能(AI)によって生み出される創作物と知財制度
・今後、人工知能によって、人間による創作物と見分けのつかない情報(AI創作物)が爆発的に生み出される可能性がある。
・そのため、AI創作物に対する保母の可能性・必要性など、AI創作物の出現に対する知財システムの在り方について検討が必要。
(3)国境を超える知財侵害への対応
・インタネット上での知財侵害行為は、海外に設定されたサーバーを利用するなど、より巧妙化、複雑化、営利目的化しているため、これら国境を超える悪質な侵害行為に対し、諸外国の例も参考に、より一層の対応強化が必要。
図 リーチサイトとサイトブロッキング
(*1)フェアユースとは -日本ではYoutubeの映像はすべて見ることができない!?-
Youtubeのサイトの著作権センターの下の「フェアユース」というリンクからたどってみると
「フェアユースとは、一定の条件を満たしていれば、著作権所有者から許可を得なくても、著作物を再利用できることを示した法原理」で、米国著作権法107条で指針を示し、あとは個別案件で検討してね、という発想だ。
107条によるとその指針の部分を抜粋すると、
ここでは、著作物の利用がフェアユースに当たるか否かについて、少なくとも下記4要件を考慮して判断されるとしている。
1. 利用の目的と性格(利用が商業性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む)
2. 著作権のある著作物の性質
3. 著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性
4. 著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響
途上国を含めて主要各国の著作権法ではこのフェアユースの考え方を取り入れているが、どういうわけか日本だけはこれを条文化してしまっている。
今後、予期しない様々な知財権に関する課題が出てくることを想定すると日本でもフェアユースの考え方を導入すべきだろう。
ちなみに他国でフェアユースを何らかの形で取り込んでいる代表的な国はイギリス、香港、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、イスラエル、台湾、フィリピン、韓国、中国、EU(Copyright Code)などである。
ちょっと横道にそれた感もあるが今回はおさらいということで、次稿以降でオープンソースライセンスに切り込んでいきたい。
2021年12月7日


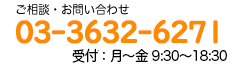

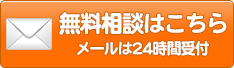
.jpg)










